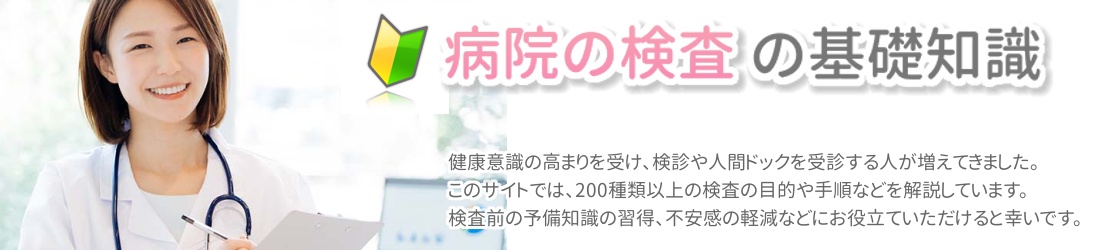心筋梗塞や脳梗塞などのリスクの目安となるリポたんぱく
コレステロールや中性脂肪などの脂質は水に溶けにくいという性質があるため、血液中ではアポたんぱくと結合して、リポたんぱくとして存在しています。リポたんぱくは3種類あり、そのなかで最も多いのがリポたんぱく(a)です。LP(a)と表記されることもあります。

リポたんぱくは、LDLコレステロールのアポB-100に、糖たんぱく質の豊富なアポ(a)が結合してできたもので、このアポ(a)は血栓を作りやすくするはたらきがあります。リポたんぱく(a)は酸化されやすく、冠動脈疾患や脳梗塞など動脈硬化が原因となる病気を促進させます。
この検査で何がわかるのか?
心筋梗塞や脳梗塞などのリスクの目安となります。血中濃度が高いほど、コレステロール値も高くなってきます。動脈硬化が進行し、冠動脈疾患などのリスクが高くなります。さらに、他の脂質関連因子、とくにLDLコレステロール値が高くなると、さらに発症するリスクが高くなります。
検査はどのように行われるのか?
血液を採取して行なわれます。基準値は30mg/dl未満となっています。
異常があったらどうするか?
動脈硬化に対しては、暴飲暴食、運動不足、喫煙、ストレスに気をつけます。リポたんぱく(a)が高いときには、医師の指示に従って食事療法などを行い、コレステロールを下げるようにします。
異常な場合に疑われること
心筋梗塞、脳梗塞などの動脈硬化性疾患、糖尿病、腎不全、ネフローゼ症候群など